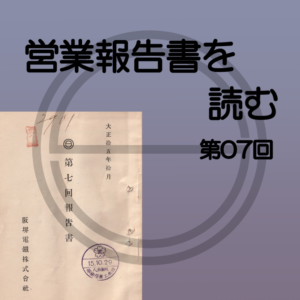電車軌道布設特許願(大正八年八月)
今回は、実業家である高倉為三をはじめとする29名の関係者が、後に新阪堺電車となる港南電車軌道の特許出願した背景とその「電車軌道布設特許願」の本文及び出願理由を見ていきたいと思います。
今回は写真がなく、文字ばかりになりますが、読んでいただけますと幸いです。
特許願出願の背景
木津川左岸地域は第一次世界大戦による世界的な船舶需要の高まりから、大小の造船所の進出が相次ぎ、活況を呈するようになりました1。その木津川左岸の内陸部について、明治期には大阪と堺を結ぶ鉄軌道の敷設(南海線、高野線、上町線及び阪堺線)が相次ぎ、また、当時既に大阪市であった木津川右岸地域(現在の大正区)について、大正期には大阪市電が敷設されました2。しかし、北加賀屋を含む木津川左岸の沿岸部分について、前述のような陸上交通の発達は遅れていました3。
北加賀屋周辺地域のさらなる発展を見込んだ実業家・高倉為三は木津川土地運河株式会社を設立し、港南電車軌道株式会社による軌道敷設による開発計画を企図し、地主や有力者に諮って4、「電車軌道布設特許願」を1919年(大正8年)8月20日に提出します。次に、「電車軌道布設特許願」の本文及び現代語訳を示します。
電車軌道布設特許願・本文
まず、「電車軌道布設特許願」の本文5から見ます。なお、原文には発起人の詳細な住所が記載されていますが、本筋には関係ないので、「◯◯」で省略しています。
原文
今般南大阪方面一帶卽チ木津川左岸ナル西成郡津守村東成郡敷津村同郡墨江村ニ亙リ造船業紡績業鐵工業等ノ諸工場續々新設セラル丶ニ伴ヒ著シキ發達ヲナシ來リ候モ是レニ適應スヘキ電鐵ナキヲ遺憾トシ一般公衆交通利便ノ爲ノ最モ急設ヲ要スヘキモノト被認候ニ付同地域一帶地主等茲ニ覺醒スル所アリ特志有力者ト相計リ港南電車軌道株式會社ヲ發起シ別紙圖面經過地線路明細書、理由書、目論見書、收支計算書、工事方法ノ通リ該地域內ノ一般公衆交通ヲ目的トシ大阪市營電鐵芦原橋停留所ヨリ堺市ニ至ル電車軌道布設特許出願致候儀ニ付別紙理由書ニ詳記セル事情ニ有之候ヘハ御洞察ノ上御認可被成下度此段奉願上候也
大正八年八月二十日
港南電車軌道株式会社発起人
大阪市南区◯◯
髙倉為三 印
大阪市東區〇〇
武内作平 印
大阪府西成郡津守村◯◯
吉川吉郎兵衛 印
同府大阪市西区◯◯
西田正俊 印【註1:1代目西田正俊】6
大阪市東区◯◯
白山善五郎 印【註2:5代目白山善五郎】7
大阪市東区◯◯
白山清太郎 印【註3:後の6代目白山善五郎】8
大阪市東區◯◯
早瀬太郎三郎 印
大阪市東區◯◯
奥谷宇之助 印
大阪市南区◯◯
宮崎敬介 印
大阪市南区◯◯
中西平兵衛 印
大阪府東成郡天王寺村◯◯
柴谷伊之助 印
大阪府東成郡天王寺村◯◯
柴谷利一 印
大阪市西区◯◯
濱田甚兵衛 印
大阪市東區◯◯
芝川又四郎 印
大阪市西区◯◯
永田三十郎 印
大阪府東成郡敷津村◯◯
櫻井重太郎 印
大阪府東成郡敷津村◯◯
櫻井昜太郎 印
大阪府堺市◯◯
大塚三郎兵衛 印
大阪府泉北郡三寶村◯◯
生島貞次郎 印
大阪府東成郡敷津村◯◯
櫻井民次郎 印
大阪府東成郡敷津村◯◯
櫻井収次郎 印
兵庫県武庫郡甲東村◯◯
河原改栄門 印
大阪市北区◯◯
井上虎治 印
大阪市東区◯◯
野田吉兵衛 印
大阪市東区〇〇
加島安治郎 印
大阪市東区◯◯
河崎助太郎 印
大阪市南區◯◯
浮田忠治郎 印
大阪府東成郡天王寺村◯◯
中川淺之助 印
大阪府東成郡天王寺村◯◯
山岡順太郎 印
内閣總理大臣 原 敬 殿
内務大臣 床次 竹二郎 殿
現代語訳
今般、南大阪方面一帯、すなわち木津川左岸にあたる西成郡津守村、東成郡敷津村、同郡墨江村において、造船業、紡績業、鉄工業などの工場が次々と新設され、それに伴い、著しい発展を遂げてきました。しかし、それに対応する電鉄がないことが残念であり、一般の人々の交通利便のために最も急いで設置するべきものと認識されております。このため、同地域一帯の地主たちが覚醒し、志のある有力者たちと相談して港南電車軌道株式会社を発起しました。別紙の図面として経過地線路明細書、理由書、目論見書、収支計算書、工事方法の通り、当該地域内の一般公衆交通を目的として、大阪市電・芦原橋停留所から堺市に至る電車軌道の布設特許を出願することとなりました。別紙の理由書に詳記されている事情をご覧の上、どうかご認可くださいますようお願い申し上げます。
(出願者29名は省略)
内閣総理大臣 原 敬 殿
内務大臣 床次 竹二郎 殿
電車軌道布設特許願・出願理由書
次に、出願理由書9を見てみます。なお、実際に提出された出願理由書は14ページにも及ぶ長いものなので、出願理由書を現代語訳し、それを要約したものを下記に示します。
出願理由書(現代語訳・要約)
工業の発展は水陸交通機関整備の速度により左右されます。大阪市が日本唯一の工業として、成長したのは秀吉や家康の時代に多くの河川が開削されたことが理由です。
現在、大阪市は水運に加え、陸上交通機関が整備され、大工業都市の色彩が鮮明になってきました。その発展とともに、同市の工業地域は市内の行政区域を越え、東成郡や西成郡の町村にまで急速に拡大しています。
工業発展には水運と陸運がバランスよく発展することが必要です。大阪市北部では水陸交通の状況は満足に近づきつつあると言えます。
それに対し、大阪市南部には木津川と十三間川があり、木津川は港湾として重要であり、十三間川沿岸には戦前【註4】より多くの工場が設置されています。特に木津川沿岸は戦時中【註4】に造船業が発展し、大型ドックの新設が進みました。戦争終結【註4】とともに多くの造船所が閉鎖されましたが、木津川沿岸の大型ドックの新設が進んでいます。
我々の出願電車軌道線は大工業地域における一般陸上交通を目的としています。新しい交通機関を導入することで、水運の利便性と陸上交通を補完し、工業発展に貢献しようとしています。そのため、志のある有力者と協力し、港南電車軌道株式会社を発起し、特許出願を速やかに進めることにしました。
南部大阪の陸上交通機関としては、南海鉄道【註5:南海本線】、阪堺電気軌道【註6:阪堺線、上町線】及び大阪高野鉄道【註7:高野線】などがありますが、距離が離れており、その沿線住民の利用に限られています。このため、木津川や十三間川の地域住民は多くの時間と費用を浪費しており、本電鉄敷設により、その欠陥を補うことができます。
大阪市の隣接町村が大阪市に編入することは時間の問題であり、その時には大阪市電が敷設されるでしょうが、発展状態にあるこの地域はそれを待つことはできません。
また、堺市の工業も大阪市と関係が深く、共に助け合っています。しかし、水運は常に使用できるわけでもなく、陸上交通は木津川沿岸から遠すぎます。本電鉄は堺港と大阪港を結ぶ重要な交通手段となり、一般の人々の利便性を向上させます。
本特許出願線路は、幅員約18mの道路を新設し、そこに電車線複線を敷設するものであり、自動車や荷車にも利便性を提供します。
【註4】ここでいう戦争は第一次世界大戦である。
この要約を更に纏めると、「大阪市南部木津川、十三間川沿岸には多くの工場が設置されるようになりましたが、水運はともかく、適切な陸上交通はないため、特許出願しました。いずれ当該地域も大阪市に編入され、大阪市電が敷設されるでしょうが、それを待っている時間はなく、また、本電鉄は堺市とも連絡するため、阪堺間の沿岸地域を結ぶ重要な交通手段となります。また、併用軌道で敷設するので、自動車等の交通にとっても便利になります。」となり、だから、特許認可してほしいということになります。
つまり、「阪堺間の沿岸地域の重要な交通機関になるし、時間もないから、認可してぇなあ。」ちゅうことやな。
CHIKAちゃん、短くしすぎ。でも、それだけが目的かしら?
では、他の文献から、その目的を探ってみましょう。
実際の出願理由について
では、実際の出願理由について、当事者に近い立場及び遠い立場の記述から考察します。
まず、当事者側に近い千島土地株式会社の『千島土地株式会社五十年小史』によると、❝東成郡敷津村地区の交通は、木津川土地運河株式会社(大正八年九月設立)社長高倉為三が、同会社の株主及び大地主である白山、芝川、浜田、大塚、中西、生島らの諸氏並びに土地会社と相諮り、地価昻騰を主目的として大都市計画完成後の工業地帯たるべき同地域の開発を期し、電気軌道敷設の企画を進めた。❞10ことが記述されています。
次に、『南海沿線百年誌』によると、❝当時木津川土地運河株式会社社長であった高倉為三が、同社株主、沿線土地会社ならびに大地主らとはかり、大都市都市計画完成後の地価高騰を目的として計画された❞11ことが記述されており、❝交通事業本来の発展を目指すというより、むしろ沿線土地の開発を意図し、併せてこの方面に利害をもつ一部大地主らの欲望を満たそうとする傾向が強かった❝12とも伝聞形式で記述されています。
この両者の記述はほぼ同じであり、出願の背景でも一部述べましたが、「木津川土地株式会社社長の高倉為三が同社株主、大地主及び沿線土地会社と相諮り、地価高騰を主目的として、(未開発だった)津守、敷津地域を開発するために電車軌道を敷設する。」のが真相だと思われます。
なるほど、要は阪急さんのやり方に倣って軌道と沿線土地の価値をあげようとしたんやな。阪急さんは電鉄会社としての思惑から始めたことやと思うけど、新阪堺電車は土地会社の思惑のほうが強かったんやな。
近い立場の記述からは関係者の名前が出ているのに対し、遠い立場の記述からは割と辛辣な評価が出てくるね。
工事方法を見ると、興味深いことが記述されていますが、これらは後日に話したいと思います。
参考文献
- 千島土地株式会社 編,『千島土地株式会社設立100周年記念誌』,千島土地株式会社,60pを参照した。 ↩︎
- 千島土地株式会社 編,『千島土地株式会社設立100周年記念誌』,千島土地株式会社,58pを参照した。 ↩︎
- 千島土地株式会社 編,『千島土地株式会社設立100周年記念誌』,千島土地株式会社,60pを参照した。 ↩︎
- 千島土地株式会社 編,『千島土地株式会社設立100周年記念誌』,千島土地株式会社,62pを参照した。 ↩︎
- 『鉄道省文書、阪堺電鉄(元港南電車)巻1 大正11年~昭和2年』(国立公文書館所蔵)を引用した。 ↩︎
- 二代西田正俊 編,『西田正俊回顧録』,ニ代西田正俊,1931年,38p,国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1101343 (参照 2024-08-18)を参照した。 ↩︎
- 『白山家のあゆみ』,白山殖産株式会社,1984年,135pを参照した。 ↩︎
- 『白山家のあゆみ』,白山殖産株式会社,1984年,135pを参照した。 ↩︎
- 『鉄道省文書、阪堺電鉄(元港南電車)巻1 大正11年~昭和2年』(国立公文書館所蔵)を参照した。 ↩︎
- 『千島土地株式会社五十年小史』,千島土地株式会社,1962年,68p,国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2496218 (参照 2024-08-18)を参照した。 ↩︎
- 南海道総合研究所 編,『南海沿線百年誌』,南海電気鉄道,1985年,119p, 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9571488 (参照 2024-08-18)を参照した。 ↩︎
- 南海道総合研究所 編,『南海沿線百年誌』,南海電気鉄道,1985年,119p, 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9571488 (参照 2024-08-18)を参照した。 ↩︎